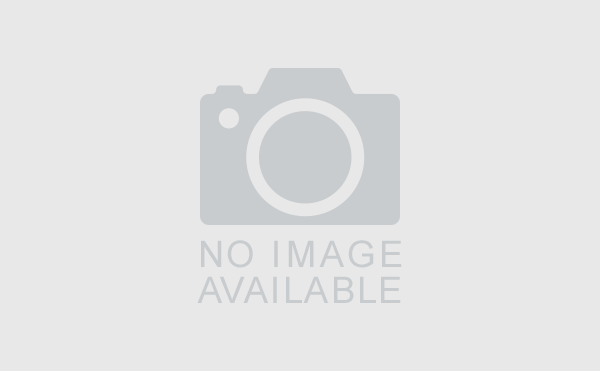想定年収と判例

今日は某大手自動車メーカーの訴訟案件から
「想定年収」の法的意味合いを考えてみます
サクっと判例から
A社で6カ月半働いた労働者が、賞与に関する期待権を侵害されたとして、
140万円の支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所は請求を全面的に棄却した
労働者側の主張は
採用通知書に記載された『想定年収』から
賞与を受給する期待権があると主張
つまり
ボーナスが出なかったせいで、
採用の時の想定年収より大分収入が少ない
ボーナス払ってくれ!
ということ
裁判所は賞与は労使交渉を経て決定しており、
示した年収額は「『想定』の域を出ず、
一定の給与を確定的に表示したとはいえない」と訴えを退けています
この判例のポイントは二つ
●労使交渉に基づき、賞与を払っている⇒労使の同意がなされている
●想定年収は1つのモデルであり、必ず提示された金額を約束するものではないこと
です
特に2つ目のポイントは重要なポイントで、
求人を出す企業としては出来るだけいい条件を提示して、
より優秀な人材を確保したいところです
当然、全く的外れの想定年収を提示することは問題ですが
優秀な社員、好調な業績の際の賞与額、を一つのモデルとして
金額を記載することも大きな問題とはならないと考えられます
特に賞与については、使用者側の裁量が大きく認められるものとなっています
採用のアドバイスはMRKK社会保険労務士事務所の古賀まで、ご相談下さい